記事概要
読了時間:7分
システム開発契約書は、システム開発における成功の鍵となる重要な書類です。本記事では契約書作成時に押さえておくべきポイントや注意点について解説します。特に、「何を盛り込むべきか」「リスクをどう回避するか」に悩んでいる方に向けて、具体的なアドバイスを提供します。
システム開発契約書とは?
システム開発契約書は、発注者(クライアント)と受注者(システム開発会社)が、プロジェクトを円滑に進めるために締結する契約書です。具体的には、以下の内容が含まれます。
- 開発範囲:どこまでを開発するか
- 納期:納品期限とマイルストーン
- 費用:見積もり金額と支払い条件
- 責任範囲:トラブル発生時の対応や保証範囲






「契約書を適当に作るとトラブルの元になります!内容をしっかり確認しましょう。」
契約書作成時のポイント
1. 開発範囲を明確にする
開発範囲を具体的に定めることは、契約書の要となります。例えば、以下のように記載します。
- 対象とするシステムの概要(例:ECサイト、業務管理ツール)
- 提供する成果物(例:プログラムコード、設計書、テスト結果)
注意点: 曖昧な表現を避け、誤解が生じないように細かく記載しましょう。






「なんとなく決めた範囲が後で問題になることも。具体性が大事!」
2. 納期とマイルストーンを設定
納期の遅れはプロジェクト全体に影響を及ぼします。そのため、以下のポイントを押さえておきましょう。
- プロジェクト全体の納期
- 中間成果物を提出するマイルストーン(例:UIデザイン提出、機能A完成)
- 遅延時のペナルティや調整方法
実例:
第1フェーズ:UIデザイン提出 - 2024年2月1日 第2フェーズ:基本機能の実装 - 2024年3月15日
3. 契約形態を選ぶ
契約形態には主に以下の2つがあります。
- 請負契約: 完成物に対して報酬が支払われる契約。成果物に対する責任が重い。
- 準委任契約: 業務遂行に対する報酬が支払われる契約。主に作業時間に基づく報酬。
選ぶ際は、プロジェクトの性質やリスク分担を考慮してください。






「契約形態の違いは支払いのタイミングやリスク配分に直結します!」
契約書の注意点
1. 知的財産権の取り決め
完成したシステムやソースコードの知的財産権については、契約時に明確にしましょう。一般的には以下の2つがあります。
- 発注者に帰属: クライアントが知的財産権を保有。
- 受注者に帰属: 開発者が知的財産権を保有し、ライセンス提供。
注意点: 双方の立場を考慮し、公平な条件を設定してください。
2. 保証期間と範囲
システム開発後の保証期間を定めることも重要です。例えば:
- 保証期間:納品後3ヶ月
- 保証範囲:バグ修正のみ対応






「“修正は全部無料”という契約は避けたいですね。費用感も現実的に!」
まとめ
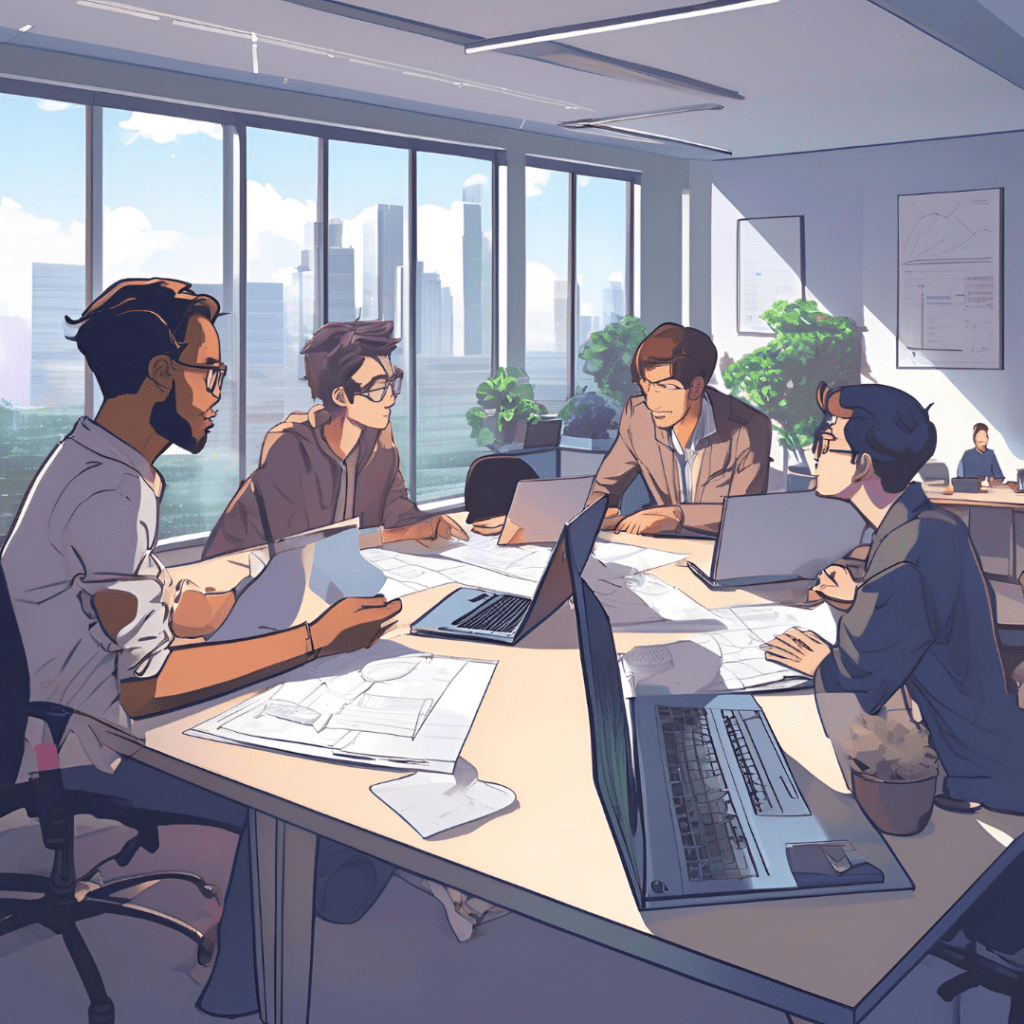
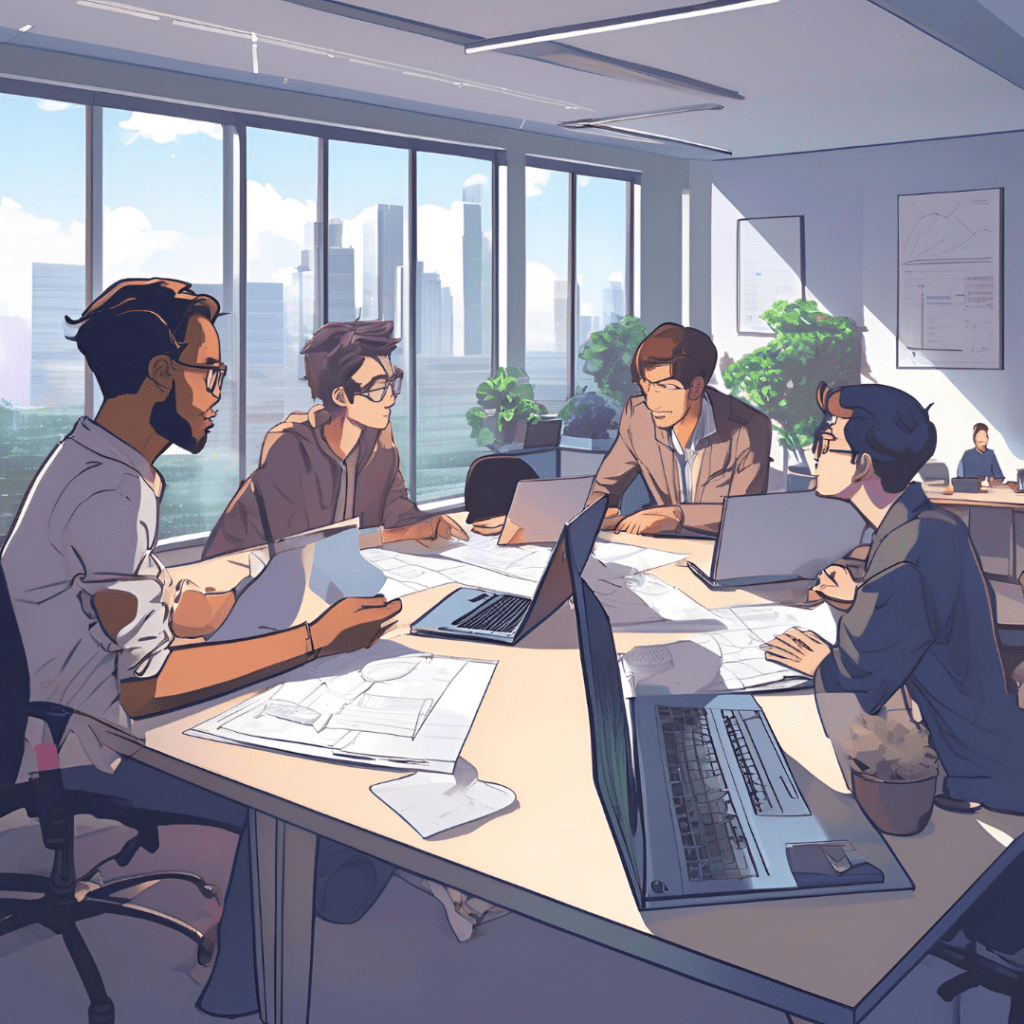
今回の記事では、システム開発契約書についてお伝えしました。システム開発契約書は、プロジェクト成功の基盤となる重要な書類です。開発範囲、納期、契約形態、知的財産権、保証範囲などをしっかりと取り決めることで、トラブルを未然に防ぐことができます。






「契約書の作成は少し面倒に感じるかもしれませんが、後々のトラブルを防ぐための大切なステップです!」
InterfaceX株式会社ではコンピュータのソフトウェア及びハードウェアの企画、開発、人材育成まで幅広く手掛けています。クライアントと丁寧に打ち合わせを重ね、クオリティの高いサービスを提供いたします。お気軽にご相談ください!



